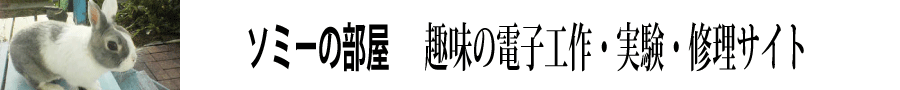
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市販品ではメンテナンス困難なので自作しました
アルミの角パイプを購入した
アンテナ・アームは2階のベランダから突き出す
メンテナンス時は、アームをスイングします
スイングアームの支点になるアルミアングル
アームを水平に支えるホルダー
スイングアームの支点になるアルミアングルの加工
GPのクランプをアームに取り付ける
アンテナ・アームを固定するクランプの製作
アンテナ・アームを取付板にクランプする
ベランダアーム改良
【運用結果とその後の改良】
|
|